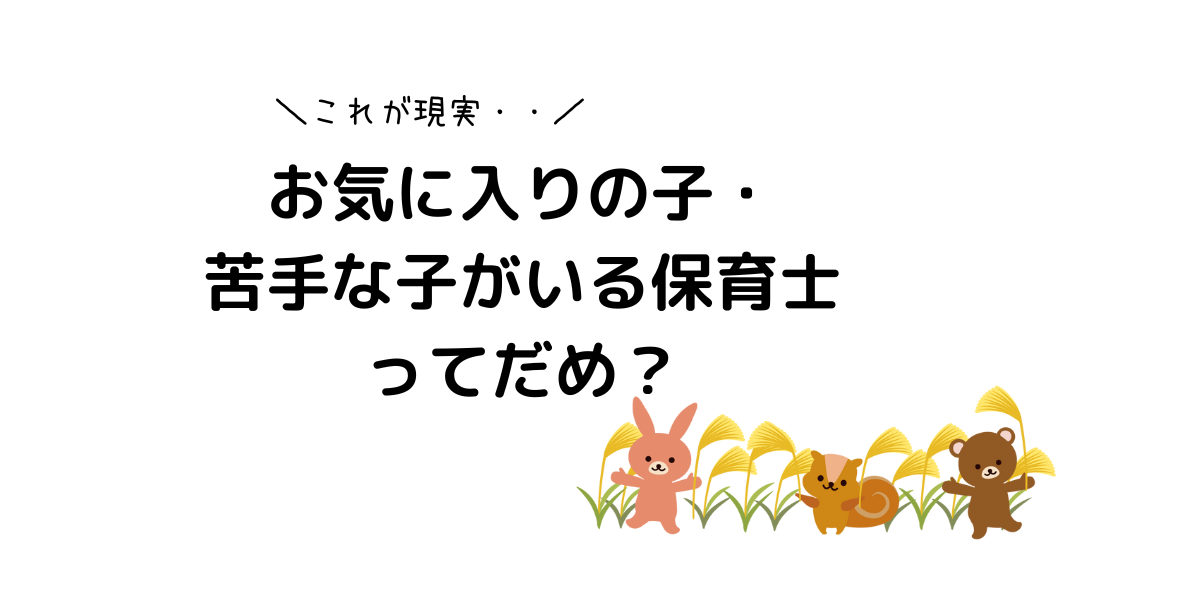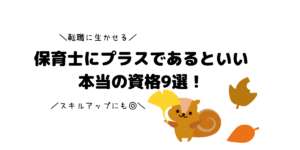30代で保育士デビューをして、現在は小児科で病児保育士をしている「かもん」です。
「ついあの子には笑顔になってしまう」
「正直、ちょっと苦手な子もいる…」
——保育の現場で、そんな自分の感情に戸惑っている保育士さんも多いのではないでしょうか。
子どもたちと毎日関わる中で、誰にでも「お気に入りの子」や「どうしても苦手に感じてしまう子」が出てくることがあります。
そんな自分の感情に「これはダメなこと?」とモヤモヤしてしまうこと、ありませんか?
 保育士かもん
保育士かもんなかなか人には話せない悩みですよね・・



本気で子供に向き合おうとするからこそ、悩みは尽きないケロね・・
この記事はこんな保育士さんにおすすめ
- 子どもによって接し方に差が出てしまうことに悩んでいる
- 「お気に入りの子」「苦手な子」ができてしまう自分に罪悪感を感じている
- 他の保育士も同じような気持ちを抱えているのか知りたい
- 感情に振り回されず、もっと子どもたちと向き合いたい
この記事を読むとわかること
- 「お気に入りの子」や「苦手な子」ができる心理的な理由
- その気持ちを否定せず、上手に保育に活かす方法
- 感情に偏らず、すべての子どもと向き合うためのヒント
この記事では、そんな悩める保育士さんの気持ちに寄り添いながら、感情との上手な付き合い方や接し方の工夫を、わかりやすく解説していきます。
感情を否定せずに、子ども一人ひとりと誠実に向き合うためのヒントを、ぜひ一緒に見つけていきましょう!
なぜ「お気に入りの子」や「苦手な子」ができてしまうのか?
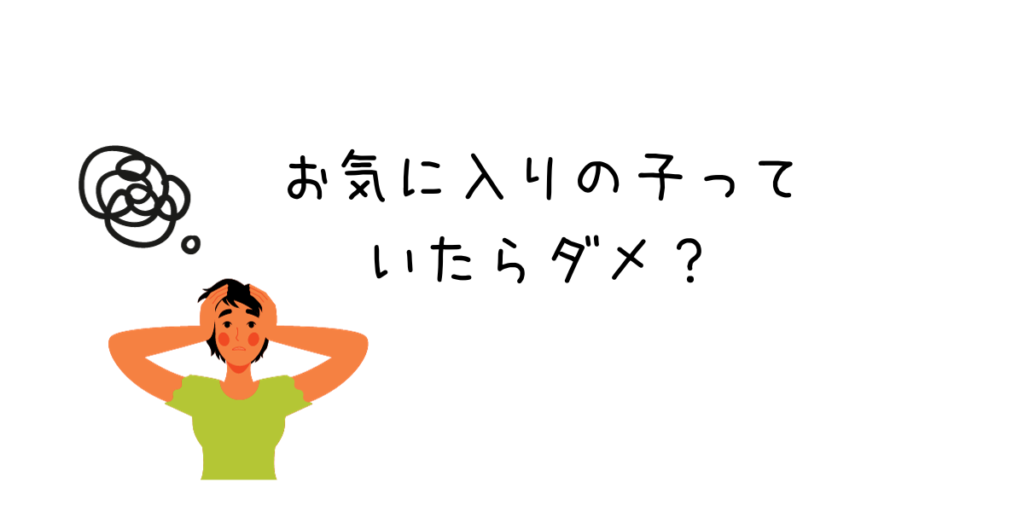
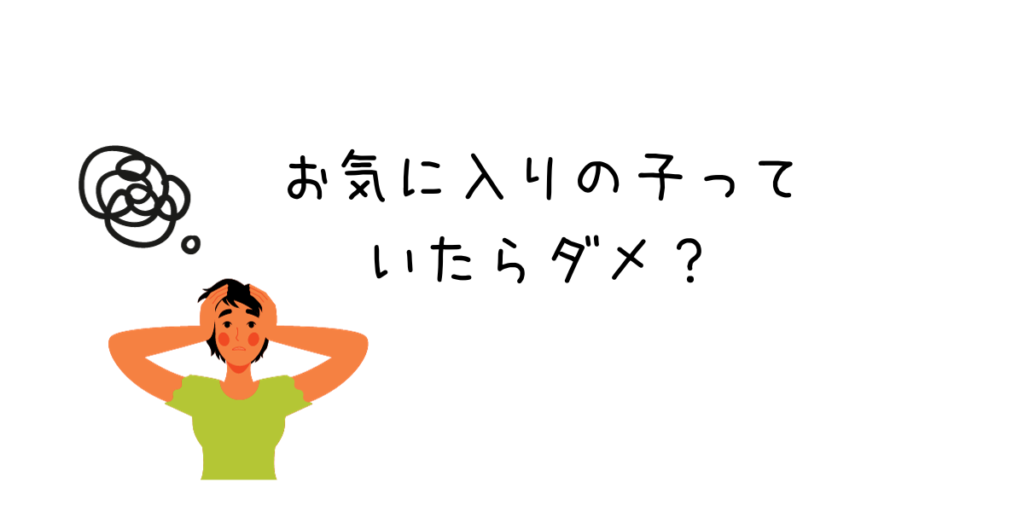
子どもはみんな平等に可愛い…そう思いたいけれど、実際の保育現場では「どうしても気が合う子」「接しづらいと感じる子」がいるものです。
そんな自分の感情にモヤモヤしてしまう保育士さんは少なくありません。
ここでは、保育士に「お気に入りの子」や「苦手な子」ができてしまう心理的な理由や背景について解説します。



あなたの気持ちを自分で理解したうえで、子どもに対してどのように接していくのが良いか考えることが大切です。
感情が芽生えるのは「人間だから」当たり前
保育士も感情を持つ一人の人間です。
相性の良し悪いや第一印象、過去の体験などから、無意識に子どもへの好意や抵抗感が生まれるのは自然なこと。
たとえば…
- 自分によく懐いてくれる子 → 愛着が湧きやすい
- いつも反抗的な態度をとる子 → 苦手に感じる
- 自分の幼少期に似ている子 → 無意識に好意や警戒心を持つ



これらはすべて、心の働きによるものであり、保育士として失格というわけではありません。
子どもとの「相性」や関わりやすさが影響する
子どもの性格や行動パターンが、保育士の感情や接し方に影響を与えることはよくあります。
- 自分の価値観に近い子 → 共感しやすい
- 自分の苦手なタイプの子 → 疲れやすい、戸惑う
ただし、「相性が合わない=悪いこと」ではありません。
相性の違いを受け止めた上で、どんな関わり方ができるかを探っていくことが大切です。
保育士自身の心の状態や経験が関係することも
保育士の「今の状態」や「これまでの経験」も、感情の偏りに大きく関係します。
▼たとえば、こんなときに感情が偏りやすい
- 寝不足やストレスが溜まっているとき
- 忙しさで心に余裕がないとき
- 昔の自分と重なるような子に出会ったとき
- 他の子との関係に悩んでいるとき
つまり、「子どもが悪い」のではなく、自分の状態によって感じ方が変わることもあるということ。
保育士に気に入られやすい子供の特徴
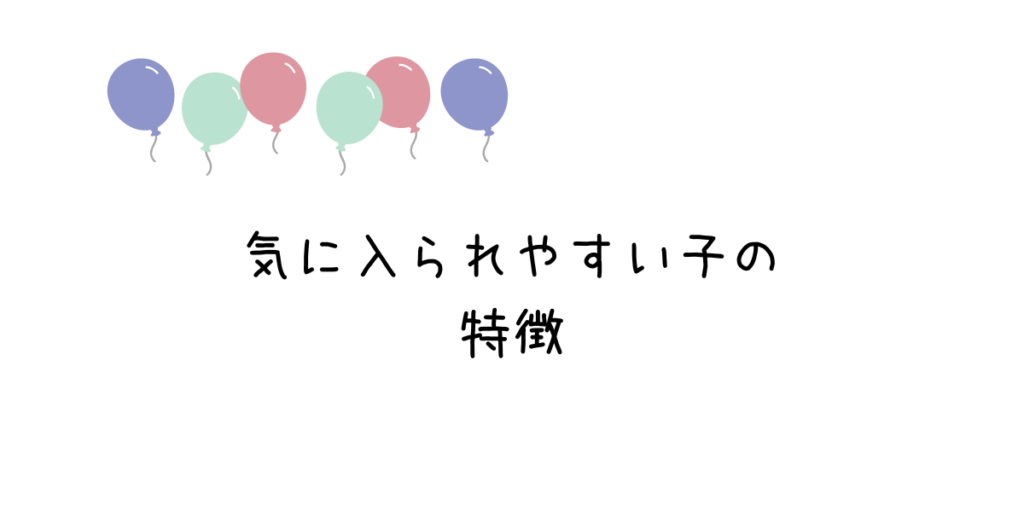
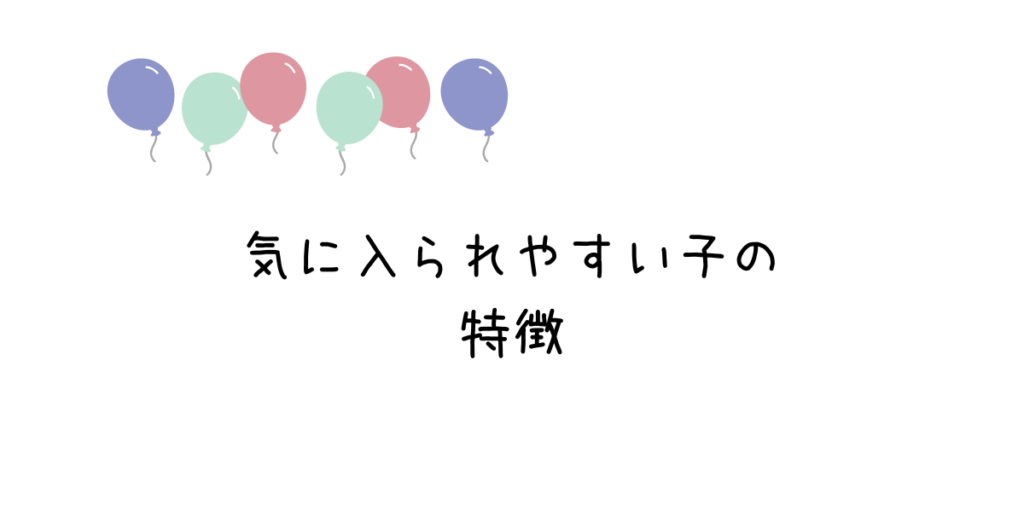
具体的にどんな子供が気に入られやすいのでしょうか?
一般的に考えられる例を紹介します。
素直で一生懸命な子
何にでも一生懸命で、保育士の言うことに素直な反応をしてくれる子は好かれます。
子供に限らず大人でもそうですよね。
特に保育士が何か指示を出したときに、しっかり話を聞いて周りに流されず行動してくれる子は本当にありがたい存在!
自然とお気に入りになっていることも多いでしょう。
保育士に懐いている子
「先生!」「大好き!」
誰しも「好き」という気持ちを注がれると嬉しいものです。
保育士に懐いてひっついてきてくれる子は、ついつい保育士もかまってしまいがちです。
子どもによってストレートに態度に出せる子と、シャイであまり寄りつかない子がいます。
普段あまり保育士に寄ってこない子がめずらしく甘えてきたり、コミュニケーションを取りに来たときにもついついキュンとしてしまいます。
手がかかるが愛嬌がある子
やんちゃだったり、マイペースだったり、、
他の子よりも少し手がかかる子に、日ごろからあれこれと接していくうちに、思い入れが強くなっていくこともよくあります。
手がかかる上に反抗的な態度ばかりでは疲れますが、ときにかわいらしい言動を見せてくれる子には情も入りやすくなります。
何かのタイミングでいつも手がかかる子の成長を感じた時には、
「あんなにやんちゃだった子が・・」
などと、ジーンときてしまったりする保育士も少なくないでしょう。
保護者が協力的で手がかからない子
保護者が保育士と良い関係を築いている場合、その子供にもいい印象を持ちやすくなります。
そのうえあまり手がかからない子であれば、保育士としては親子ともに好意的な存在になるでしょう。



保護者が協力的って、保育士としては本当にありがたいですよね!
保育士が苦手に感じやすい子供とは
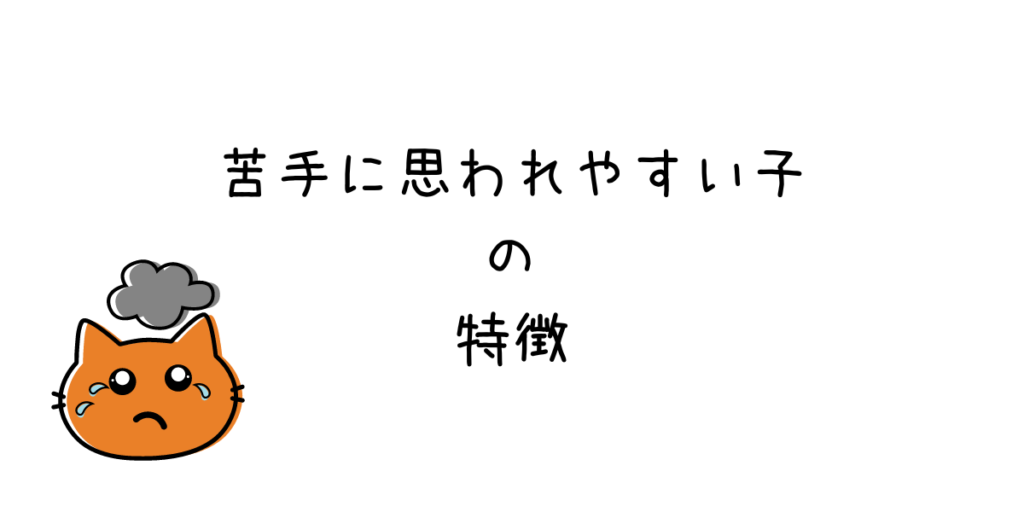
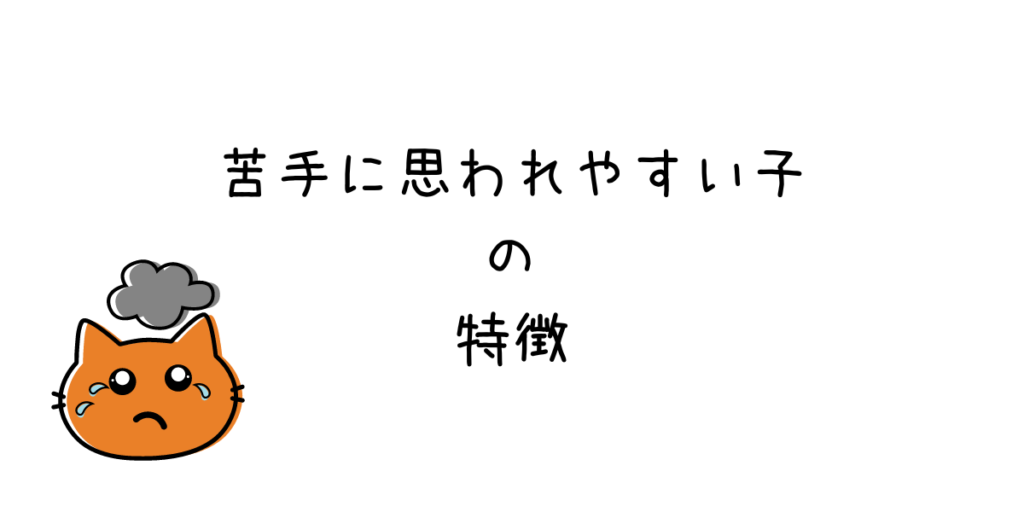
お気に入りに感じる子がいる反面、苦手に感じてしまう子がいるのも事実です。
具体的にどんな子が苦手に感じられやすいのでしょうか。
保育士に反発ばかりする子
何を言っても保育士に反発したり、暴言を吐いてくる子はいます。
保育士も人間ですから、ついつい苦手意識を持ってしまうことはあります。
特に行事前の忙しい時期や、保育士に余裕がない時にはイラっとしてしまうこともあるでしょう。
保育士への依存が強すぎる
保育士にたいして、依存が強すぎる子もいます。
気をひきたくてわざと困らせてきたり、つねに保育士にくっついてきたり。
そんな子どもの行動に疲れてしまう保育士は苦手意識を持ってしまうこともあります。
保護者がクレーマー
わが子かわいさのあまりにあれこれ口うるさい保護者はいます。
保育士は保護者のクレーム対応に追われると精神的にまいってしまいます。
保護者がクレーマーな子は、保育士として必要以上に気を使ってしまったりなんだかモヤっとしてしまう・・なんてことも。
発達に不安がある子は負担が大きい場合も
苦手とは少し違いますが、発達に不安がある子は保育士にとって手がかかる場面が多くなるのが現実です。
例えば、かんしゃくを起こして物を投げてしまったり、じっとできずに部屋の中を走り回ってしまったり・・
保育園側が保育士の人数を充分なだけ配置してくれているかというと、実際はギリギリの人数で回している園がほとんどです。
そのため保育士にとって大きな負担となってしまうこともあります。



発達グレーの子は年々増えています。
保育士の配置基準の見直しを本気で考えてほしいですね・・
「お気に入りの子」への接し方で気をつけたいこと


保育士として働いていると、どうしても「この子、かわいいな」と思える子がいますよね。
言葉づかいや仕草、表情が愛らしく、こちらも自然と笑顔になってしまう——そんな経験、誰にでもあると思います。
でも、その気持ちのまま関わっていると、他の子どもたちから「えこひいき」と見られてしまうリスクがあるのも事実。
ここでは、お気に入りの子との関わり方で意識したい3つのポイントを解説します。
えこひいきに見えないためのバランス感覚
どんなに一人の子を可愛く感じていても、保育の場は集団の中での公平さが求められる場所です。
他の子どもたちはとても敏感で、「先生は○○ちゃんばっかり」と感じた瞬間、距離を置くようになったり、信頼関係にひびが入ったりすることがあります。
✅実践したい工夫:
- 関わる時間・声かけをできるだけ均等に
- グループ活動では意図的に違う子と組む
- 写真・制作物なども“特定の子ばかり”にならないよう注意



見た目の公平さを意識するだけでも、子どもたちの安心感は大きく変わります。
気持ちを言語化し、客観的に見つめ直す
「なぜこの子に惹かれるんだろう?」
「なぜこの子ばかり気にかけてしまうんだろう?」
そんなふうに自分の感情を一度言葉にしてみることは、とても大切です。
たとえば・・
- 「あの子は昔の自分に似ていて気になる」
- 「甘えてくれることで、自分の存在意義を感じられる」
このように掘り下げることで、無意識だった“依存”や“保育士としての満足感”への欲求に気づくことができます。
気づいたうえで、「子どものためになっているか?」と立ち返ると、自然とバランスが取れていきます。



好き嫌いがあってもなくても、子供にはみんな平等!
これ基本ケロ~~
他の保育士と気持ちを共有する
感情を1人で抱え込んでしまうと、「私だけこんな気持ちになるなんて…」と、罪悪感が膨らんでしまいます。
でも実際には、多くの保育士が同じような感情に悩んでいるのです。
他の保育士と感情を共有することで、自己否定のループから抜け出し、冷静な視点を持てるようになります。



もし信頼できる相手が身近にいない場合は、日報やノートに書き出すだけでもOK。
感情を外に出すことが、客観性を取り戻す第一歩になります。
「苦手な子」との関わりに悩んだときの考え方
「またこの子が泣いてる…」
「反応が薄くて関わりづらいな」
そう思ってしまう子どもとの関係に、内心で戸惑っている保育士さんは少なくありません。
苦手だと感じること自体は悪いことではありませんが、そのままにしておくと関わりが薄くなり、子どもとの信頼関係に影響することも。
ここでは、「苦手だな」と感じる子とどう向き合えばよいのか、心構えや具体的なアプローチをご紹介します。
「なぜ苦手なのか?」背景や理由を探ってみる
子どもの行動には、必ずその子なりの理由や背景があります。
- 癇癪を起こす → 自分の気持ちを言葉にできない
- 指示に従わない → 注目されたい、主導権を握りたい
- 無表情・反応が薄い → 家庭での関わりが少ない、安心できる人がいない
あえて関わる時間をつくってみる
「つい避けてしまう」
「自然と他の子に目がいく」
そんなふうに感じているなら、意識してその子と1対1で関わる時間を作ることがとても効果的です。
こんな関わり方がおすすめ
- 登園・降園時に目を見て名前を呼ぶ
- 食事や着替えの介助を積極的に担当してみる
- 得意な遊びや好きな話題にさりげなく入っていく



関係性は「関わること」でしか築けません。勇気を持って一歩踏み出すことで、子どもの反応も変わっていきます。
苦手と感じる自分を責めすぎない
「子どもを苦手に感じるなんて、自分は保育士に向いていないのかも…」
そんなふうに落ち込んでしまうこともありますよね。
でも、それは決しておかしなことではありません。
大切なのは、「苦手=ダメなこと」ではなく、「気づけたこと」がすでに前進であるという考え方です。
心をラクにする考え方
- 感情に「良い・悪い」はない。あるのは「どう受け止めるか」だけ
- 苦手な子がいるからこそ、自分の感情と向き合う機会がある
- 苦手意識はずっと続くわけではなく、関係の中で変わっていくことも多い



自分の弱さや感情を受け入れることで、保育士としても人としても深みが増していくケロ♪
感情に振り回されず、子ども全体と向き合うには?
保育の現場では毎日いろいろな出来事が起こります。
嬉しいこともあれば、イライラしたり、不安になったりする日もあるでしょう。
「お気に入りの子ばかり気にかけてしまう」
「どうしても苦手な子を避けてしまう」
そんなとき、「全体を平等に見ないと…!」と自分を追い詰めてしまいがちですが、大切なのは感情に流されすぎず、子ども一人ひとりと丁寧に向き合うこと。
ここでは、そのための感情整理の方法・視野の広げ方・プロ意識の持ち方について具体的にお伝えします。
日々の振り返りで感情を言語化する
まずは、自分の気持ちを「なんとなく」で終わらせず、言葉にして整理することから始めてみましょう。
やってみたい振り返りの方法
- 保育日誌やメモ帳に、印象に残った子どもとのやりとりを書く
- 「なぜその子にイライラしたのか?」を自問してみる
- 「今日よかった関わり」「もっとうまくできたかも」を具体的に書く
感情を言葉にする=自分を客観視する習慣が、保育のバランス感覚につながっていきます。
子ども一人ひとりの「よさ」に目を向ける習慣
特定の子に気持ちが偏るのは、無意識のうちに「よさ」に気づいているからです。
逆に言えば、他の子にも意識的に「よさを探す視点」を持てば、自然と関心のバランスが整っていきます。
🌟こんな取り組みが効果的
- 毎日1人、「今日の観察ターゲット」を決める
- 小さな行動や成長にフォーカスしてメモを取る
- 苦手な子ほど「いいところ探し」を意識する
子どもたちはみんな、違った形の魅力や強みを持っています。
その子らしさに目を向けることで、自然と全体を見渡せるようになります。
保育士としての「プロ意識」を思い出す
感情に流されそうになったとき、最後に頼れるのは自分の中にある「保育者としての軸」です。
意識したいプロの視点
- 子どもを「好き・嫌い」で見るのではなく、「育ちの過程」で見る
- その子がどんな発達段階にあるのか、どんな関わりが必要なのかを冷静に考える
- 感情が揺れたときこそ、「なぜこの仕事を選んだのか」を思い出す
感情を完全になくす必要はありません。
ただ、保育士としてどう関わるか?という「軸」を持っていれば、揺れにくくなります。
身近にお気に入りの子を優遇する保育士がいたらすべきこと
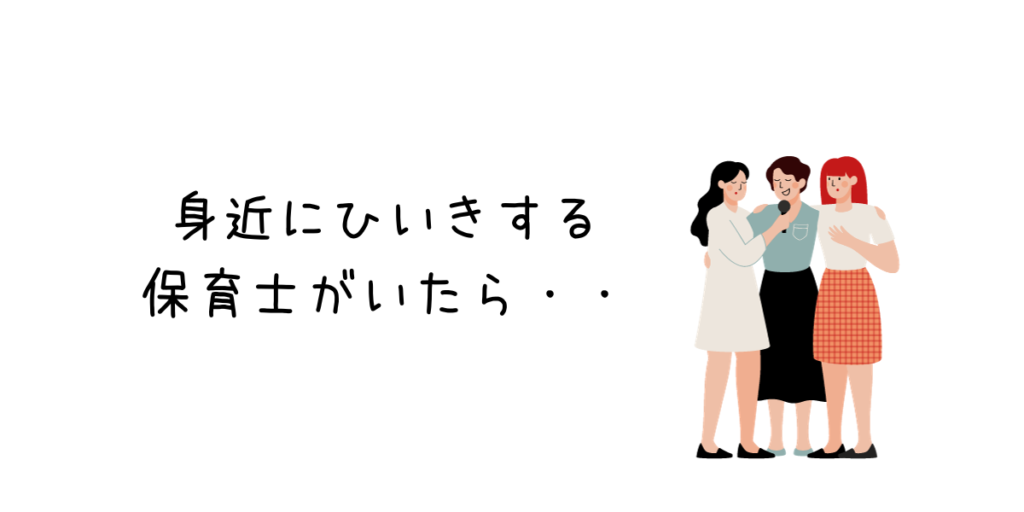
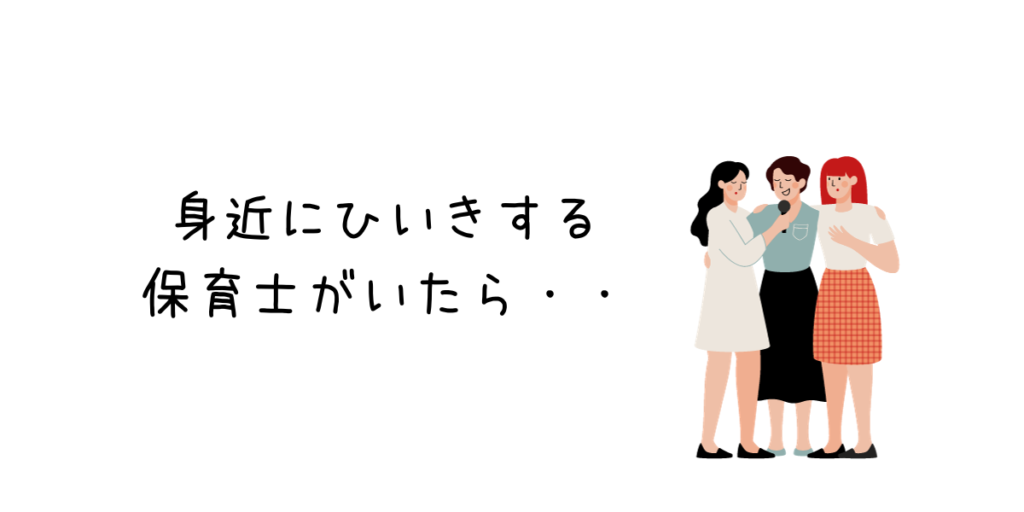
自分はお気に入りの子をひいきしたり、苦手な子に冷たい態度をとっていない人でも、身近な同僚に好き嫌いで態度を変える保育士がいる場合もありますよね。
そんなときの対処法は以下の2点です。
気持ちに共感してから本人に伝える
自分より後輩であったり何でも言える相手であれば、自分が感じたことを上手に伝える努力をしましょう。
「気持ちはわかるんだけどね・・」
と共感してから、自分が客観的に見て感じたことを本人に話してみましょう。
意外と本人は無意識にやっていて気付いていない‥ということもあります。
主任やリーダーなど信頼できる人に相談する
現場の雰囲気が悪くなりそうで、直接伝えるにはなかなか勇気がいる・・
という人は、主任やリーダーなどの経験豊富で信頼できる人に相談しましょう。
上司から上手に本人に話してくれたり、さりげなくフォローしてくれるかもしれません。
見て見ぬふりはしないようにしましょう!
エスカレートして不適切保育につながってしまう可能性もあります。
なにより辛い思いをしている子をほったらかしにしないようにしましょう!
どうしても子供を平等に見られない人は転職も視野に入れよう
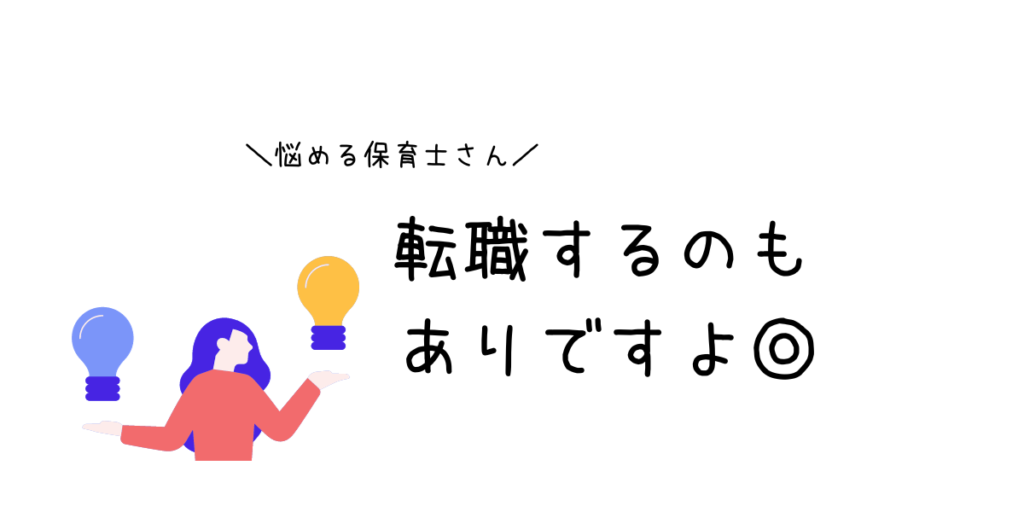
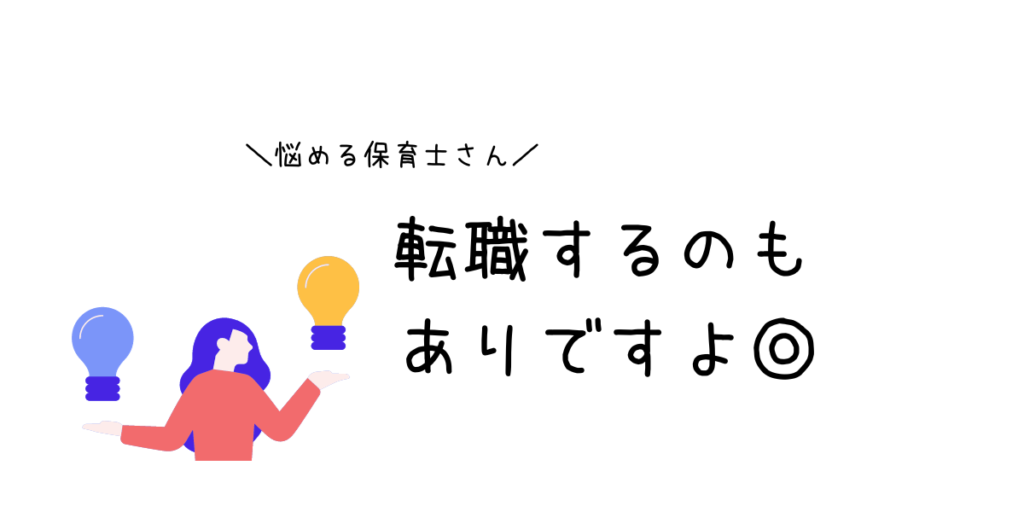
頭では子供を平等にしないといけないことがわかっているのに、どうしても自分の気持ちが抑えられず態度を変えてしまう・・
こんな人は思い切って転職を考えてみるのもありです。
保育関係でも、少人数でじっくり子供と関わることができる託児施設やベビーシッターなど、働き方は色々選択できます。
自分の心にあまり負担がかからないような職場を、一度探してみることをおすすめします。
▼子供とじっくり関わることができる園に転職したい人、待遇のいい職場に転職したい人!
転職エージェントに登録してあなたの希望条件を伝えるだけで、自分に合った職場を探してくれます☆
登録~就職サポートまで完全無料◎
▼保育士から一般企業への転職はここ!
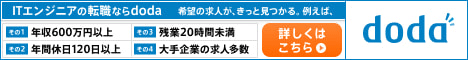
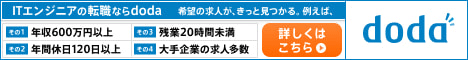
▼保育士からアパレルへの転職ならここ!
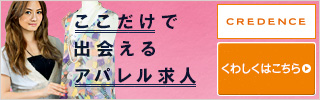
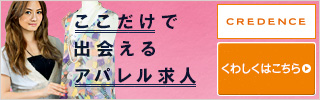
まとめ:感情を受け入れて、保育に活かそう
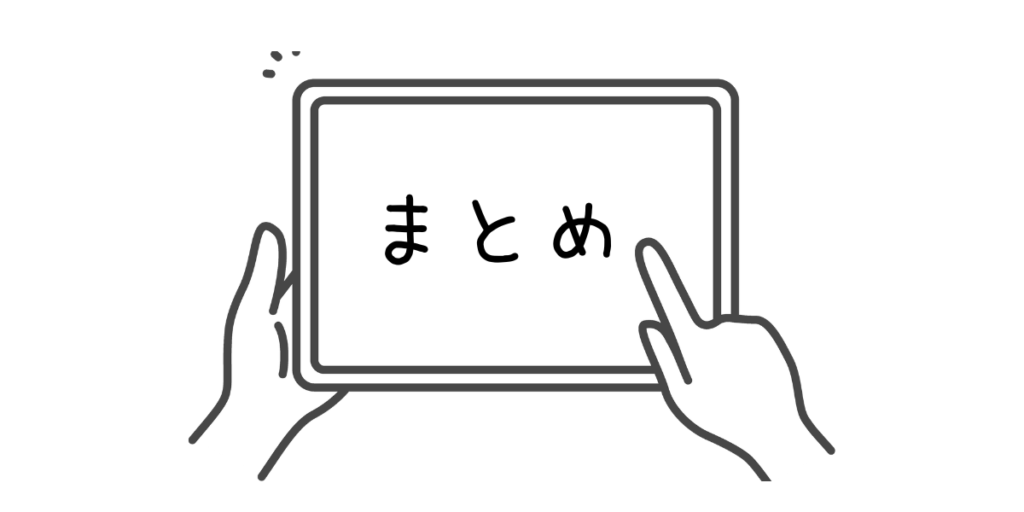
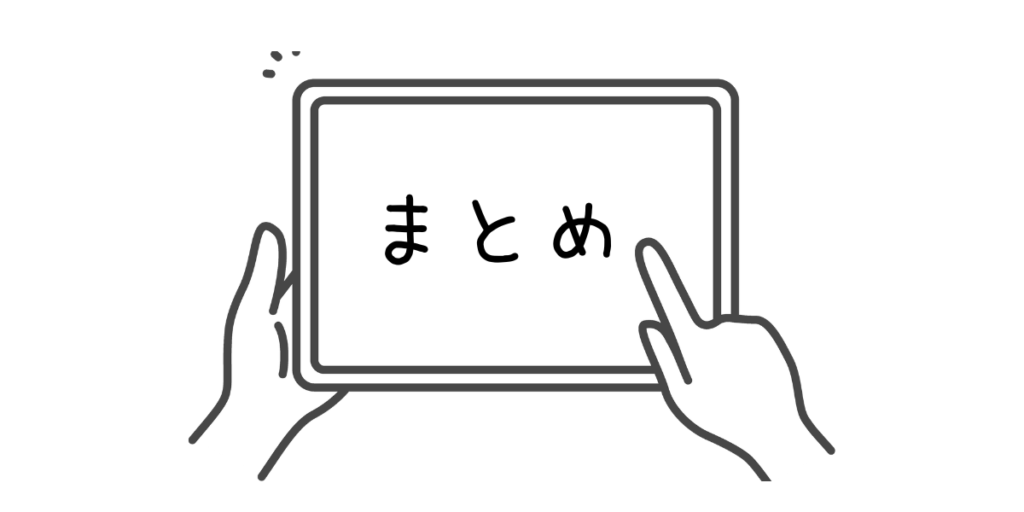
「お気に入りの子」や「苦手な子」ができてしまうのは、保育士として失格だからではなく、人間として自然な感情です。
大切なのはその感情を否定せずに、自分の内面を見つめ直し、よりよい関わり方を模索していくこと。
- 感情を言語化し、振り返る習慣をつける
- 子ども一人ひとりの「よさ」に目を向ける
- 同僚と気持ちを共有し、プロとしての視点を忘れない
日々の小さな気づきや工夫の積み重ねが、子どもたちとの信頼関係を深め、保育士としての成長にもつながります。
完璧じゃなくて大丈夫。感情があるからこそ、あなたの保育には“あたたかさ”が宿ります。
明日からまた、子どもたちと丁寧に向き合っていきましょう。
おすすめの転職サイト(すべて無料で利用できます)
| 転職サイト | ポイント | 対象地域 | 公式サイト |
|---|---|---|---|
| 保育士 ワーカー | 保育士支持率NO.1! 非公開/好条件求人が多い 手厚いサポート体制 | 全国 | |
| 保育士 人材バンク | 保育専門のパートナーがサポート 上場企業が運営で安心! 保育関連職も豊富 | 全国 | 保育士人材バンク |
| ジョブ メドレー | 自分のペースで転職活動できる しつこい勧誘や電話なし! スカウト機能アリ | 全国 | |
| 保育の お仕事 | 専任のアドバイザーがマンツーマンでサポート 応募先の内部情報がわかる 非公開/好条件求人が多い | 全国 | |
| レバウェル 保育士 | 6か月以内のスピード転職はおまかせ! 履歴書・面接対策あり LINEでいつでも気軽に相談可能 | 全国 ▼首都圏 多め |